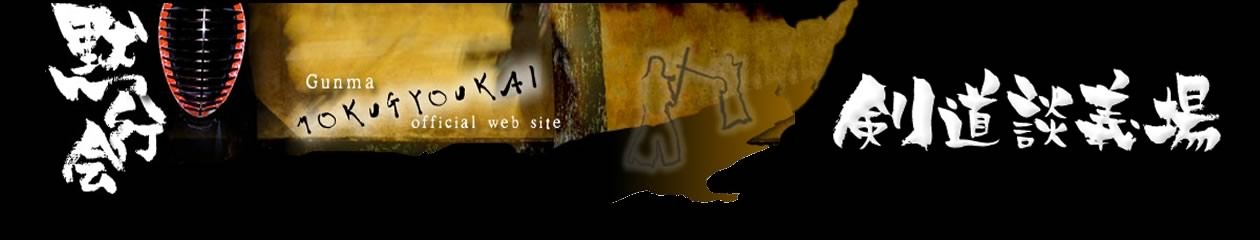2月3日は節分。朝の冷え込みと日中の暖かさの気温差が大きく感じられる今日この頃です。
火曜日になってようやくJ大寒稽古の筋肉痛が治まってきました。日曜日に行われた中学生の試合の審判をしている時は会場が寒かったこともあって筋肉が硬直しているのが分かります。しかし、それで旗を上げられないという事態にならないよう試合を受け持つ前にストレッチなどしてみました。
火曜日のM署ではかなり身体が動くようになって次の寒稽古(O体大)に向けて体調が整ってきています。しかし、毎回楽しみにしている支部稽古会を諸般の事情から今週は欠席予定です。でも、その代わりと言っては何ですが自分の剣道の質を高めることで少しでも還元できるように今週末からの寒稽古で再度厳しく鍛えられてきます。
そうそう、J大寒稽古のバーチャル体験をしてみたい方は浅見先生のブログ http://gkendo.exblog.jp/ に載っていますのでそちらをご覧ください。

予告通り、G玉一行は金曜日の夜からJ大入りし、土曜日の寒稽古をして帰ってきました。
到着してすぐに大学の先生方による酒宴のおもてなしを受けることになり、近くのお店に伺ったところ、そこには顔がほんのり桜色になっている浅見先生もいらっしゃいました。
浅見先生は当剣道談義場をよくご覧になっているそうで、「ここでの話をどう(当談義場で)表現するか真価が問われるぞ。」と飲食に夢中で酔いが回っている私に厳しい課題を課せられます。浅見先生と谷先生との会話のやり取りの中で多岐にわたるヒントが垣間見えましたが、一番印象深い言葉としては「どう感じるかだ」という一言。大病して人生観が変わったという浅見先生だからこそ発せられる重みのある一言です。
ご指導を受ける、良い剣道を見る・体験する等々についてどう受け取り、どう感じるかは千差万別。感じ方によって上達速度も違ってくることでしょう。浅見先生ご自身は既に「浅見流」を確立されておられる点においては自分のスタイルを早く確立することを見習う必要があるかも知れません。文書表現能力も剣道実力も不足で上手く表現できませんでしたが、浅見先生には近日中にご指導を受けるチャンスがあるのでそこでまた学ばせて頂きます。
早朝の寒稽古には「自己流」の言葉で有名になった大学生で日本一の選手も参加しており、注目を集めていました。寒稽古の内容はいつも通りで一生懸命な大学生に負けないように私も集中力を切らさないように努めました。案の定、終わった頃には声がかすれ、汗まみれで腕は上がらなくなり、足腰もガタつきました。特に切り返しや体当たりを受ける影響でふくらはぎの辺りがパンパンです。
でも終わると気持ちがいいものです。心境としては祐さんの剣道手帖の中にある「剣道に学ぶ・サトウハチロー」http://yusannokendo.blog.fc2.com/blog-entry-110.html
に通じるものがあります。*ジバンとは「ジュバン・襦袢」つまり剣道着のこと。
剣縁に恵まれ、こういう場所で寒稽古ができただけでもありがたいことです。関係者の皆様には大変お世話になりました。

月曜日のI島道場は先週行われるはずだった道場開きがの雪の影響で25日に延期されたことからタイミングよく私も神主さんにお祓いをして頂きました。この行事に参列するといつも気持ちがピリッと引き締まります。
火曜日のM署は大人の先生が極端に少ない反面、中学生が極端に多い珍しい光景となりました。中には初心者に近い人もいて、ぎこちない動きがあるものの、ほんの少しアドバイスするだけでそのぎこちなさが解消する人がいました。なかなか上手く出来ない人でも不器用な私に比べれば飲み込みが早いうちに入ります。
木曜日の支部稽古会も中高生と多く稽古し、反省点として中高生相手に捨て切れない自分がいるということです。しかも無駄打ちや正確さに欠ける打ちが何本もあり、そういう意味でもまだまだ修行不足です。
という訳で、自分の修行のために今週末は本県からT八段、U兄弟先生、S玉県からN岸先生と共にJ大寒稽古にお邪魔してきます。足腰が立たなくなるくらいこってり絞られるだろうなぁ~。

年初めの黙行会は平野部にしては大雪の影響からか、概ね普段の2~3割減の参加者となりました。が、しかしそこは黙行会。T八段、M田八段の両八段が顔を揃え、中身は決して薄くなることはありませんでした。個人的には道場が広く使えた分、打ち抜けを意識してみたり、多様な技を出そうと心掛けたりと若干の工夫をしてみました。
稽古終わりにT八段から「師匠に見てもらえる有難さ」という内容のお話がありました。自ら出身大学の寒稽古に赴き、稽古を師匠や先輩に見てもらい、指摘された点を心に留め、自分の剣道を見直そうと思ったとのこと。一流の先生が一流の先生に教えを受けるのはどんなものなのか興味深いものがあります。
第2道場では剣道談義の他、これから向かうであろう大学の寒稽古の日程調整も行われました。「寒稽古」という響きだけでも身震いがしてきます。いつものことながら「行くも地獄、行かぬも地獄」の心境です。
毎年、寒稽古に行って後悔したことはないので今年も実り多きものになりそうですが、いかんせん、この時期が精神的に一番不安定になります。「安心して下さい。」と誰かに言って欲しいものです。
次回の黙行会は2月16日(火)19:00~となります。

金曜日の朝、TVをつけると本県に近い国道でのバス事故の痛ましいニュースが大々的に報じられており、上空ではヘリコプターや小型飛行機が目的地目指して飛んでいき、家の中にいても時折プロペラ音が聞こえてきます。犠牲になったのは将来のある若い人たちが多いと聞き、本当にお気の毒な限りです。心よりご冥福をお祈りいたします。
木曜日の支部稽古会はようやく通常モードに戻った感じで中高生をはじめ多くの参加者で賑わいました。元立ちの先生方が少なく私は元立ちとして稽古をさせて頂きました。1番手から女子高生が若さ全開で掛ってきます。こういう時は受けに回りがちになりますが、そこはこちらから先を掛けるつもりで臨みます。
しかし、初っ端の女子高生からかなり打たれ、ガチンコで臨んでいるだけに「自分が弱くなった?」と心の動揺を隠し切れません。その後に続く別の女子高生にも良いポイントでしっかり打たれ、心が折れそうになりながらも徐々に調子が戻ってきたのがせめてもの救い。後から考えれば「若い人の成長を目の当たりにして嬉しい。」と捉えたほうが正しいのかも知れませんね。精神衛生上も落ち込まなくて済みますし。
稽古が終わって、ある先生から使わなくなった方が所持していたという「木鶏」と揮毫された竹刀袋を頂戴しました。「木鶏」は横綱双葉山が69連勝でストップした時に「未だ木鶏たりえず」と打電したことで有名になった言葉です。その双葉山の69連勝がストップした日がなんと!1月15日ということで何かの因縁を感じます。まるで剣道の神様から「もっと精進しなさい!」と叱咤されているかのようです。

11日は鏡開き。我が家でもおしるこや焼餅にして美味しく頂き、また、この連休に成人式があったことから街中では振袖姿の女性をよく見かけました。
私はこの土日、一級審査会のお手伝いと県剣連新年会に参加してきました。土曜日の一級審査会当日は高校の入試日と重なり、混雑が予想されましたが、時間を少しずらしたためさほどの渋滞はなく、遅刻した受審者はいなかったので、まずは一安心。天気も良く気温が高い上、昨年から入ったエアコンのお蔭で道場内はポカポカと暖かい審査会となりました。結果はともあれ、「審査に向けて準備をすることが重要」という副支部長の言葉が的を得ていたように思います。
日曜日の県剣連主催新年会は有功賞の受賞のお祝いをはじめ中高生の10傑表彰などお祝いムード一色。しかし、お酒が入るとすぐに剣道談義が始まるのが剣道家らしいところ。剣道家には正月も鏡開きもあまり関係ない?かも知れませんね!
そうそう、鏡開きから出てきた剣道姿の「ゆるキャラ」もよろしくお願いします。

新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
2日はやや冷え込んだものの正月元旦から3日まで実にいい天気でした。3日は真冬とは思えない暖かさ。まさに新春ですね。
こんな天気に恵まれた三が日に各地の稽古会に参加してきました。まず正月元旦は支部稽古会。県外の先生方や他支部の先生方に加えて学生・生徒さんも多く参加して盛大に行われました。支部のHPにもその様子が写っていますが、安心してください、表紙の写真は大人の先生方のみの写真で高校生以下は「写真ギャラリー」に掲載されています。
2日はF支部の三ヶ日稽古会に参加。朝が早かったため一番の冷え込みを感じました。I田八段、N山八段の両八段に稽古をつけて頂き、短い時間ながらも実のある稽古会となりました。N山八段のご挨拶の中で「今年は申年。一説では実のなる年になるそうです。また、変革の年でもあると言われています…」と、それを聞いて言葉が身体の中で溶けていくようにスッと入ってきました。すぐにでも実現するような予感(剣道以外かも?)!
3日はI市のT澤道場へ。昨年は道場の門下生が高校総体個人出場や全日本選手権大会に出場するなど結果を残した県下でも屈指の道場です。師範のW辺八段をはじめ県内全ての八段の先生、その他名立たる先生方が勢ぞろいされ、子供から大人まで道場に入り切れない恐ろしい人数が顔を揃えました。それでも私は館長先生にキッチリと、これぞ稽古!というような厳しい打ち込み稽古をつけて頂きました。同道したT八段が掛ってくるお相手に対して打ち込んでいたのとは全く意味が違う「打ち込み」であることは言うまでもありません。
色々な場所、様々な剣風に触れることは本当に刺激になります。今年も許す限り出稽古をしたいと思いますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。

22日は冬至。我が家では柚子湯とかぼちゃは欠かせない定番アイテムとなっています。柚子湯の効用はともかく、柚子湯に入っているだけで季節感が味わえます。最近では一年中見かけるかぼちゃでさえも何となく季節感を出しているように思います。
23日は午前中に支部主催の2・3級審査、1級講習会が行われ、そのお手伝いに行ってきました。例年と一番違うところは武道館内に暖房が入ったことでしょうか。今年の夏過ぎ頃にエアコンが設置され、酷暑の稽古環境が改善されたことはまだ記憶に新しく、今回暖房が入ったことでまたその恩恵を感じました。
夕方からは久しぶりに県連主催の稽古会に参加。祝日かつM支部の忘年会と重なったこともあり、いつもの半分程度の参加者でしたが、ベテランの先生方といい汗を流すことができました。
稽古前にある先生が「この祝日にクリスマスパーティーをしている人が多い。」と話せば「クリスマスって歳でもないだろう!」と別の先生。確かにクリスマスと言えば昔は特別行事感がありましたが、最近では全くと言っていいほど自分の中でクリスマスの盛り上がりがありません。これも季節感の消滅の一つかも知れませんね。
寒いとか暑いとか、クリスマスだとか正月だとかが薄まりつつある昨今、忘年会だけは毎年コンスタントに増えて楽しんでます。

今年最後となる支部稽古会は多くの参加者で賑わいました。私も気合が入り、一番にT八段にお願いすることが出来ました。実は黙行会では稽古時間が短縮されたことからT八段と稽古納めができなかったため、最後のチャンスが巡ってきたという訳です。
T八段から繰り出される面に何度か居ついてしまったことを思い出す中で、はっきり自覚したことは「気」を詰める作業の中に相手を居つかせる「技」があるのではないかということ。局面としては面を打つ前段の一瞬。それが極意の一部なのかも知れませんね。
稽古前に「剣道談義場を初めて見た。」という先生に声を掛けて頂き、「随分と奥ゆかしい表現をしてるね。」とお褒めの言葉?を頂戴しました。私の外見と文中のイメージが一致しないか、もっとストレートに表現した方がいいよ!というアドバイスなのか、「奥ゆかしいという」言葉はなんとも捉えどころがありません。ということで今回は「居つき」について頑張ってストレートな表現をしてみましたがどうでしょうか?
T八段に稽古をつけて頂いた後は老若男女問わず高校生からベテランの先生までたっぷりとしごいてもらい、忘年会続きの身体から一気にアルコールの混じった?汗が吹き出しました。今年の支部稽古会はこれで終わり。でも年内はまだやっているところにお邪魔することになるでしょう。
そうそう、黙行会第2道場でのメガネの忘れ物は無事持ち主に返りました。めでたしめでたし。

今年最後の黙行会は稽古&忘年会ともに例年以上の盛り上がりを見せました。
数多くの先生方にご芳志を頂戴したり、道場使用料についての予想を超えるご高配を頂いたりしましたこと、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
海外からもいらっしゃるなど大変な盛況ぶりについつい恒例の『今年一年の反省と来年への抱負』を忘れてしまいました。次回来年の黙行会に持ち越させてください。
忘れと言えば、忘年会会場にメガネの忘れ物がありました。H先生が保管してくださっていますのでお心当たりの方はご一報ください。

群馬県内で行われる剣道稽古会の黙行会(もくぎょうかい)