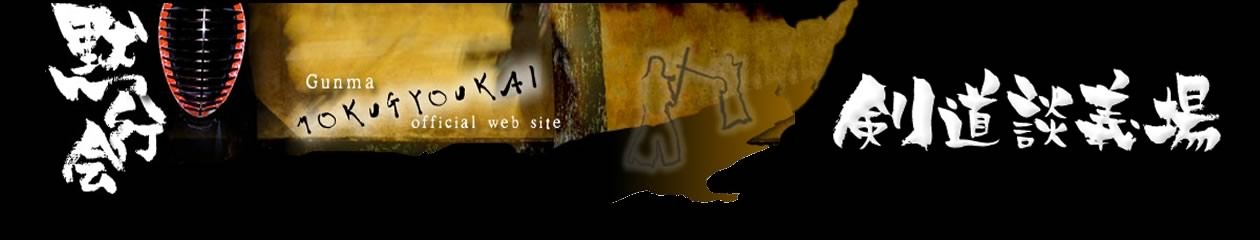土曜日の夜はS道場の稽古に参加してきました。そこでの話題は八段1次審査を通過されたN曽根先生とU山先生のお話。端的に総括すると、1次審査ではお2人とも完璧な立合いだったようです。誰もが期待した2次審査では惜しくも通過なりませんでしたが、受審される全ての先生方を含め次回に期待です。
話は4日の朝稽古に戻ります。3日に直前で終わってしまったK井範士から「明日一番でやろう!」と声を掛けて頂いたこともあり、まずはK井範士にお願いしました。開始から身動きがとれないくらいの大混雑で構えている最中に隣と接触するなど前後に動くだけでも容易でない状況の中、K井範士にはことごとく先を取られて打ち込まれてしまいました。先月行われた八段戦の2回戦でK井範士とT八段が対戦されたのを思い出されたのか、稽古終わりの挨拶で「T八段によろしく!」と一言付け加えられました。多数の掛り手がいるなかでそういった言葉がスッと出ることはスマートで格好がいい。そういうところも勉強になります。
この日の朝稽古は、八段4名の先生にお願いし終了。剣風の違う先生に触れることができ、お願いした全ての先生に合気で稽古をつけて頂いたことは本当にありがたいことです。つづく

GW中の2~5日はいっとき雨に降られたものの概ね天候に恵まれ、剣道をするには絶好のコンディションでした。私は2日の午後、八段審査の見学から始まりました。
八段審査で印象深かったのは「ひげじい」さんのコメントに返信した通り、高齢の先生が素晴らしい立合いをされたことです。出す技全て決まるなど神がかり的な光景を目の当たりにした気がします。
翌日3日の朝稽古はS道範士、S野範士の両範士に掛り、午後からの中堅剣士合同稽古会では八段の先生4名にお願いするなど充実した一日となりました。
午後からの稽古会には全30名中八段戦優勝者2名を含む八段の先生が12名参加。稽古内容は非常に厳しく、そろそろ1時間経ったかなぁと時計を見るとまだ20分程度しか経っておらず、疲労度は通常の3倍増。お蔭で懇親会での最初のビールは最高に美味しい一杯でした。
懇親会では10期上の先生方とも剣道談義に花が咲き、剣道王国九州の熱さ(飲みっぷり・剣道に取り組む姿勢など)を感じる場面が幾度かありました。強い地域にはそれなりの理由があるものですね~。つづく

日曜日は所属団体のソフトボール大会。約20年ぶりにボールを握ることになりました。1回もバットに当たらないと恥ずかしいので、バッティングセンター通いをして何とか体裁を整えてその日を迎えました。
結果は3打数3安打。久しぶりにしては上出来です。しかし、我チームのピッチャーが崩れ、急遽私がピッチャーを務めることになったから、さあ大変。四球だけは避けようとストライクを取りに行ったところを各打者の餌食となってしまいました。
やはり、全く準備ないままでは上手くいきません。翌日は身体のあちこちが筋肉痛。特に投げ込んだ肩甲骨周辺がパンパンで、火曜日になってようやく癒えてきたところです。
火曜日のM署稽古会では多くの方と稽古をお願いし、いい汗を掻くことができました。同じ汗でもソフトボールと剣道では全く質が違いますね~。でも、たまにはソフトボールも気分転換にいいものです。

熊本県を震源とする地震はその後の余震も含め甚大な被害が出ていることが日を追う毎に明らかになってきています。亡くなられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
19日の黙行会は昇段審査も間近に迫ってきているからか、県内外及び外国から40名近くの先生方が参加され、盛況に行われました。外国から参加されたのは海外在住の本県出身の先生で40年前にはT八段とインターハイ出場の座を競い合った仲だとか。時を超えての交剣知愛となったようです。
稽古では下座が一列で座り切れなくなるか?という程の盛況ぶりを見せつけられましたが、八段の先生2人が参加されるなど質も高い内容だったと思います。
座礼後のT八段の講話の中では「試合で勝とう勝とうと思わない、審査で受かろう受かろうと思わない。」というフレーズが非常に印象に残りました。試合中はどうしても勝ちたいという意識が強くなり、審査を受ければ多分受かりたいという気持ちが高まってくるに違いありません。いつまで経ってもコントロールが難しいですね。
5月の黙行会は17日(火)と決まりました。次回もよろしくお願い致します。

新年度に入って支部稽古会には新入生と思われる生徒さんも加入し、大勢の参加者で賑わいました。
気温が上がってきたからか、稽古の後半になると息が上がってくるのが分かります。ここから如何に耐えられるか真価が問われるところです。まだ4月というのに今からこれでは先行きが思いやられます。
さて、17日は八段選抜大会が行われます。支部稽古会に参加されていた先生方も何名かT八段の応援に行かれるとのこと。私も毎年楽しみに観戦していますが、今年の大会は如何に?
本大会を皮切りに今年度の試合シーズン始まりです。

7日は市内の小中学校の入学式。せっかくの晴れ姿なのに一日中冷たい雨に降られて関係者にとっては生憎な天候となってしまいました。翌日の8日は県立高校の入学式・始業式があったようでいよいよ新年度の始まりです。
さて、木曜日支部稽古会は年度替わりで中高生の姿は少なく、大人中心の稽古会でした。私は掛り手に回り、一番にT八段にお願いすることができました。T八段は八段選抜が間近に迫っていることから技の確認や体の運びなど調整に余念がありません。どこに意識を置いているか拝見しているだけで勉強になるところもあり、貴重な稽古となりました。
先日の国体1次予選(自分の試合)を改めて振り返るとチャンスはありながら、体が流れて決めきれなかったとか、技が単調だったとか、起こりが分かり易かったとか負けるだけの原因は数多く頭に浮かびます。
新年度になって心機一転、新たな気持ちで一歩でも半歩でも前進できればいいですね~。

春爛漫。校庭の桜の下で遊ぶ子供達を見ながら麗らかな心持になる今日この頃です。
さて、月曜日はI島道場へお邪魔してきました。このところメキメキと力をつけてきた小中学生も交え、約1時間先生方にみっちり稽古をつけて頂きました。
稽古が終わってある先生に挨拶に行くと「面がへっぴり腰になっている」とのご指摘。「小手はいいんだけどなぁ~」と如何にも残念そうな表情を浮かべながらのダメ出し。自分では徐々に改善しつつあると自負していただけに久しぶりに現実を突きつけられました。
私もよく、中高生に腰について指摘することがあります。以前は自分が出来ないのに人に物申すのにためらいがありましたが、最近ではあまり気にならなくなりました。相手も成長して自分も成長すればいいだけのことですからね。
色々と環境が変わる新年度に向けて気持ちも新たにしたいものです。

26日の土曜日、北海道新幹線の開通や市内に遊戯施設が開園するなど明るいニュースがありました。特に市内の遊戯施設は昔、剣道大会を催していた場所であり、姿形を変えて遊び場が出来たことは嬉しいことです。
さて、日曜日はある高校で行われている中高生合同合宿に参加してきました。試合稽古を見ていると良い所を打つ生徒さんもいて、なかなかやるなぁ~という印象。
ところが、地稽古になりいざ中高生と立合うとしっかり基本ができている人もいれば、当てることが上手い人もいて四苦八苦。タイミングが合わず何本か打たれることもありました。ここをどう捌くか考えるのも修行の一つです。
稽古後の講和でT八段が「基本が大事」という内容を話されました。確かに基本が出来ていないと上に行けません。肝に銘じて基本を見直したいと思います。

22日の黙行会はK川県のK山八段をお迎えした上、3名の初参加の先生も含め盛大に行われました。
また、八段の先生3名をはじめ、県を代表する先生などが多く参加され、寒さが緩んできた影響もあるかも知れませんが、いつもより早く息が上がりました。強者ばかりの2分刻み回り稽古はちょっとした地獄?を味わっているかのようです。
第2道場ではK山八段を囲んで盛り上がり、いつものことながら飲み過ぎました。K山八段やM田八段からお話を伺うと、同感するところもあれば、自分とはレベルが違うと感じることもあり、大いに刺激になります。
色々な先生方が参加され、真剣な稽古と楽しい懇親会は何事にも代えがたい貴重な時間です。今回も行って良かった!と思える3月の黙行会でした。
次回の黙行会は4月19日(火)となります。皆様のご参加、よろしくお願いします。

この連休はあちこちで剣道行事が行われたようで、関係者の方はお忙しかったのではないでしょうか?
私も土曜日に久々の2部練を行い、ゲッソリして帰ってきました。しかし、剣縁を感じる出会いもあり、楽しく稽古をさせて頂きました。
さて、22日(火)は黙行会です。今回の黙行会は他県から八段の先生が初参加されるとのことです。皆さん、奮ってご参加ください。
ということで、稽古後には平成28年の集合写真を撮りたいと思いますのでご準備のほどよろしくお願いします。

群馬県内で行われる剣道稽古会の黙行会(もくぎょうかい)