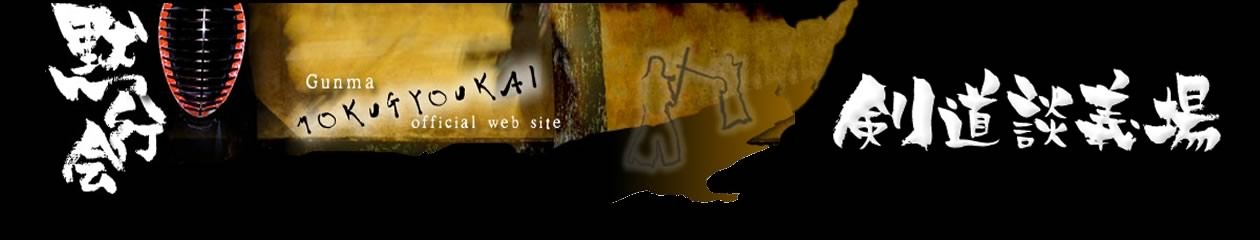T八段、U兄弟先生と4人で本県を発ったのは27日の夕刻。高速を飛ばしてJ大近くの居酒屋に飛び込んだのが夜の8時過ぎになりました。U先生が予めJ大監督N先生とやり取りしていたためN先生と浅見先生の6人で小宴会となりました。
車の中で「海のある県はやっぱり刺身」という話をしながら来たので、刺身とお酒のイメージが既に出来上がっていました。しかし、ビールで乾杯した直後、浅見先生から「この人(私のこと)は談義場で俺にワインをおねだりしてきたから今回はO体大に持っていかない!」とまずは挨拶がわりの先制口撃を受けてしまいました。
話を伺うと「与えられるだけではなく、自分から何か(モノじゃなく話題でも)を与えていく気概が必要である。」という意味だとのこと。改めてそうおっしゃられると自分が与えられるモノは何だろう?と少し考えましたが、答えは見つからず。少し悩むもそれはそれとしてイタリアの話とか大学の話とか興味深いお話を肴に楽しい時間を過ごすことができました。
28日の起床は4時40分。5時10過ぎには体育館でS玉N岸先生と合流し、5時30分から準備運動、素振り、座礼があり6時頃から切り返しが始まりました。30分程度経過後には掛り稽古に移行。私も徐々に体当たりを増やしていきましたが、T八段やU先生の体当たりからすれば優しかったかも。体当たりは掛る方も受ける方も厳しいのです。優しかったと言いつつ、家路に向かう車中では左のふくらはぎはパンパン、肩から腕にかけてはコチコチに固まっていましたけど…
地稽古になるとT八段以下G玉郡勢は全員浅見先生にお願いしました。果たして浅見ワールドを崩す者が出たかどうかはご想像にお任せします。その後、私は元立ちに立ち、関東や全日本学生で上位を占める学生さんの実力を存分に堪能させて頂きました。
寒稽古はその場の空気感を味わう魅力が大きいですね。厳しい空気感は体感以外得られません。仕事の関係で行くことが難しかった今年も無理してJ大寒稽古に行けてよかったです。疲労と睡魔のなか午後から仕事に戻ったのは言うまでもありません。

24日はかなり冷え込んだ中、通常通りの黙行会。外は厳しい寒さでしたが、道場内は丁度良い気温に調整され快適に稽古ができました。
稽古内容は最近の稽古不足を反映してやや浮足立つ場面があり、お相手より出遅れてはいけないと思うと今度は機が熟していないところで出てしまうなど空回りしてしまいました。修練不足が如実に出てしまった結果です。
稽古後のT八段の講話では「名こそ惜しけれ」について語られました。恥ずかしいことをして名前を汚すな、つまり恥ずかしいことをするなという意味と捉えてよさそうです。鎌倉時代から武士の倫理観のバックボーンをなしてきた言葉で日本人の意識の中に脈々と受け継がれてきた精神かも知れません。最近はドラマで「逃げるは恥だが役に立つ」という番組が流行ったようですけど…まぁそれはドラマなので。恋ダンス、練習したいと思ったのは自分だけでしょうか?
第2道場はK楽園でお鍋を囲み、あつあつ、ホクホクしながらビールにワイン、お酒と焼酎を堪能。冬の料理はお鍋が最高ですね。身体が温まります。
次回の黙行会は2月21日(火)です。来月もよろしくお願いします。

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。
今年の初稽古となる支部の元旦稽古会には市・県外からも多くの方が参加され、盛大に行われました。おかげで道場が狭くて困りましたが、その狭さもあと少し。来年度からは新体育館に場所が移ると支部長からお話があったので新道場に期待しましょう。
さて、昨年末ようやく仕事が一段落したので先月発売の剣道雑誌を買いに本屋に行ったところ、寒稽古でお世話になっている大学の記事やT八段が解説されている記事が目に飛び込んできました。O体大の稽古はある程度想像できますし、T八段に至っては身近で稽古をつけて頂いている先生なので頭では理解しているつもり。ですが、文面から溢れる並々ならぬ努力や継続性は、「一流との差」を痛感したところでもあります。
と同時に努力が足りない自分にヒヤッとしたのも事実です。こういう記事を読んで反省する機会は「自分に甘い路線」を修正する転機になってむしろ有難いことです。
ということで年頭にあたり今年の稽古をしっかり取り組んで参ろうと決心しましたので(剣道談義場のカキコは引き続き不定期となりますが)、どうぞよろしくお願い申し上げます。

13日の黙行会は年末のお忙しいところ、30分早まったにも関わらず、初参加の方も含め多くの先生方にお集まりいただき、いつもながら盛況な黙行会となりました。
皆様からお預かりした道場使用料は忘年会の場でT八段から会場校の先生にお渡しされましたこと、この場をお借りしてご報告と共に皆様のご協力に心よりお礼申し上げます。
忘年会での圧巻は今年の反省と来年の抱負を一人ずつ述べられたこと。それぞれ様々な事情を抱えながら、理想を描き、そこに向かって努力されていることが良く分かりました。「第2道場」とはよく言ったものでとても勉強になります。
ただ、自分の番になる頃にはほろ酔いを取り越して呂律が回らず、いつもながら何を言ったか定かでありません。
来年1月の黙行会は24日(火)となります。来年もよろしくお願い申し上げます。

12月に入り、いよいよせわしない季節になってきました。しかし、妙に生温かな気温で暦と体感に違和感を覚えます。
木曜日の支部稽古後に事務局長から先日の全国審査会で合格された先生方のご披露があって、和やかで温かな雰囲気に包まれました。合格された先生お1人ずつ一言ご挨拶をされた短い言葉の中にそれぞれの物語があり、興味深く拝聴しました。いずれにしても大変おめでたいことです。
稽古ではT八段を始め、元立ちの先生方にお願いし、気温が高いこともあってか、久しぶりにしっかりと汗を掻くことができました。T八段からは「前で対応すること」のアドバイスを頂き、重心の位置や初動からの剣体の運び方、心の置き所等を再度確認する必要を感じました。
これから忘年会シーズン、一日おきに飲み会が入っているのでお酒を外に出すため?に剣道ができるときはしっかり汗をかくように頑張りたいと思います。

気づけば11月も終わりに近づき、今年も残すところあと一か月となってしまいました。全国審査が終わると年末の準備に取り掛かる方も多いのではないでしょうか。
今年は例年以上に剣道以外でバタバタして落ち着く暇がありません。それでも細々と剣道は続けることができ、先日は仕事の予定が変更になり、急遽鑽士会に参加させて頂きました。数年後に控える審査まで身体が動くかどうか、これからの稽古にかかっています。
今は稽古できるだけでありがたい状況。しかし、こういう時の方が「降りてくるもの」が多くなるのが不思議です。何はともあれ今週も全力でいきましょう!

今月の黙行会は審査前にしてはやや少なめの参加者ではありましたが、イタリアからお越しくださいました先生や遠く関西地区からお見えの先生、専門学校生が初参加して頂くなど、新鮮な稽古会となりました。
関西地区からお見えになった先生はO体大でいつもお世話になっている190㎝を超える大柄な先生。わずかな時間でもこの地に足をお運び頂くのはとても有難いことです。
T八段との体当たり稽古はそこに居た目撃者しか分からない、レアな稽古風景でした。
それもレアではありますが、稽古後にT八段がおっしゃった「出頭は応じ技ではなく、攻め技である」という言葉は印象に残りました。審査を受審される先生方だけでなく、それ以外の先生にも心に残ったはずです。審査に向けて力が注入されましたね。
なお、来月12月13日(火)の黙行会は開始時刻が30分早まり、18時30分からスタートします。忘年会も兼ねて懇親会も行う予定ですので皆様のご参加よろしくお願い致します。

先日の大統領選の決定により、政策の不確実性から日本の株価は乱高下しました。今後、日本経済の先行きにどう影響するか、興味のあるところです。
大統領選とは全く関係ないはずの木曜日の支部稽古会は過去最多人数に匹敵する大変な賑わいの稽古会となりました。大統領選の影響ではなく、全国審査会や地区の大会が間近に迫ってきた影響だとは思いますが…。
元立ちの先生方もそれなりにいらっしゃいましたが、掛り手がかなりの数に上ったため、元立ちの先生に対してそれぞれ長い列になりました。私は元立ちに立たせてもらったので中高生から大人の先生まで大勢の方と稽古ができた反面、審査前の調整にお見えになった先生にとっては見取り稽古(待つ時間)が長く、ちょっとお気の毒でした。
稽古の参加者は多い方が活気があるし、得るものは大きい気がします。アメリカの人口はまだ増えているようですが、日本は人口減少の局面に入っています。取りあえず、まだ人がいるうちに剣道しておきましょう!

25日の黙行会は元J大教授のK先生ご一行様をお迎えした上、多数の先生方の参加も頂き、盛況に行われました。
残念ながらK先生にお願いすることは出来ませんでしたが、K原先生やT八段との立合いを拝見させて頂きました。大学の同窓生ということもあり、打った打たれただけでなく、傍で見ている者には分からない心のやり取りを感じました。
また、大学の教え子のU兄弟先生との稽古は目を見張るものがあり、厳しくも師弟愛を感じる稽古ぶりは稽古を見守る先生方の心にも残ったのではないでしょうか?
第2道場ではK先生から剣道の伝統文化継承に対する熱い想いだったり、心根の問題だったり、格の問題だったり、ためになるお話を多数伺うことができ、たいへん有意義な時間となりました。また、一刀流のお話は奥が深く、現代剣道とは一線を画す興味深い話題でした。
さて、11月の黙行会は15日(火)と決定しました。審査前の調整も含め、先生方のご参加、よろしくお願い申し上げます。

玄関にある金木犀が良い匂いを放ち、秋を深呼吸したくなる季節になりました。先週お休みだったためか支部稽古会の参加者はいつもよりやや多いように感じました。
さて、数日前に京都で仕事関係の国際会議があり、13ヶ国から16団体、約700人が集まりました。公用語は当然英語。ヘッドフォンを通じて複数の同時通訳が英語から日本語へ、日本語から英語へとスラスラ通訳していきます。本当は通訳なしに聞き取れるのが理想ですが、今の実力は時折知っている単語が続けば何となく聞き取れる程度。コミュニケーションができるレベルに至るまで相当な時間が必要と痛感しました。
会議に先立ち、基調講演を行った著名な建築家であるA藤氏は「価値をつくる」ことをテーマの一つとして講演をしました。A藤氏によれば「そこでしか見られないもの」の価値が大きいと言います。例えばオブジェや美術館など世界的に有名な人が作った芸術作品や建造物はそこに行かないと見ることができない。すなわち代替がきかないため価値が生まれるというわけです。
なぜ京都が世界的に人気の観光都市になったかと言えば京都にしかない神社仏閣、舞妓さんや芸妓さんのいる伝統文化など魅力があるからに他なりません。
剣道も伝統文化の一つ。外国でも徐々に認知されてきているようです。外国人に見せるために稽古をしている訳ではありませんが、外国人が見た時に美しさを感じさせる剣道ができればいいですね~

群馬県内で行われる剣道稽古会の黙行会(もくぎょうかい)