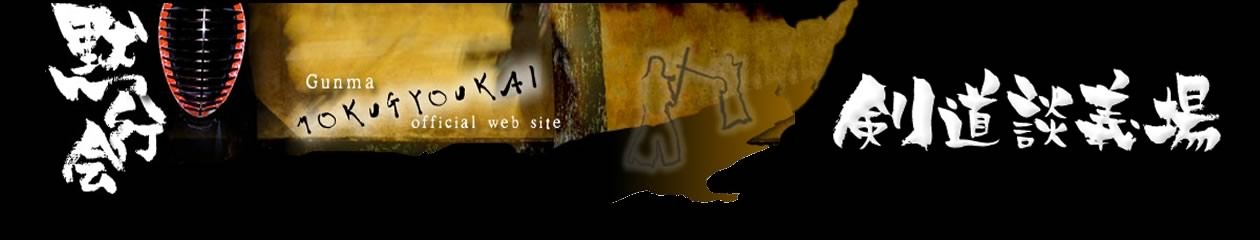いっときの酷暑を思うと最近は涼しく、残暑の実感がわかない今日この頃。
撮ってもらった全日本予選会のビデオを昨日になってようやく見る気になり、10分足らずの自分の試合を見ることにしました。試合技術や技の切れなどが足りないのは自分でもすぐに理解しましたが、身体の動きは目を覆うほど酷くなかったのは少し救いでした。
ただ、技術も心が押されている場合には出し切れません。つまり、勝つためには「勝つ技術の習得+稽古量」が必要ということになるのでしょうか。
今回優勝した選手は1日に2部練、3部練をしていることもあるやに聞きます。さすがにそこまでの稽古量の確保は難しくとも衰えをカバーするだけの稽古はしていきたいものです。
今週末はT八段が出場される都剣連主催の八段戦が行われるので、そこでレベルの高い試合を拝見してきたいと思います。

日曜日は全日本予選会が行われ、選手として出場してきました。私のお相手は最年少の選手。図らずも最年長になった自分と最大年齢差になってしまいました。
しかし、試合になればそんな事は何の関係もないので自分の持てる力を出せるように心掛けました。前回の段別戦の反省から、居つかないように足を動かしてみるようにしましたが、延長の後、上段からの鋭い打ちに小手を切られ、1回戦敗退に終わりました。
試合は稽古以上に思うようにいかず、お相手の圧力に身体のバランスを崩したり、千載一遇のチャンスを一本に決め切れなかったりと反省材料が満載になります。
まだまだ気力の衰えを感じることはなく(ないつもり)、試合で勉強出来るのは貴重な経験であることは間違いありませんが、年齢という現実を突きつけられると心に秋風が吹き始めます。まぁ、あまり深く考えず、これからもやれることをしっかりやっていくだけですけどね。
それにしてもベスト8くらいからの試合はどの試合も見応えがありました。選手・役員・審判の先生方、お疲れ様でした。

火曜日はM署稽古会に参加しました。いつもの参加者の他、AZKの先生が4名参加されており、その内の先生3名と稽古させて頂きました。噂通りの気迫ある攻め。こちらも負けてはおれず、気持ちだけは遅れないように気を付けました。
その他にも絶好調のT原先生をはじめ多くの先生に稽古をつけて頂き、「自分のイメージ」通りにはならなかったものの気持ちのいい稽古会となりました。
木曜日恒例支部稽古会は大人中心でしたが、中には数名の中高生もいる夏休み最後の稽古会となりました。私ははじめ掛り手に回り、先生方に掛かっていきました。ここでも「自分のイメージ」を持って臨むこととしました。
もうお分かりだと思いますが、「自分のイメージ」とは剣道授業のDVDを意識してのイメージです。稽古前にも先生方とその話題になり、色々な感想を伺いました。
ちなみに自動車に積んだDVDは運転中、音声のみ。停車毎に映像が流れるようになっているので信号待ちも苦にならなくなりました。車中はいつも緊張感が張りつめていますが…

月曜日は書店に行き、剣道月刊誌を購入し、早速付録のDVDを拝見しました。
細部に渡り、端的で分かりやすい仕上がりになっているのではないでしょうか。しかも、極意があちらこちらに散りばめられており、少しでも習得できれば大きな収穫があるような気がします。
昔、ある高名な先生が「私の全てを教えたとしても、皆教えた通り出来ない」とおっしゃっていたそうです。たとえ頭で理解できたとしても身体や心の動きが自分の思うようにいかないという意味だそうです。それだけ奥が深いのでしょうね~。
しかし、頭で理解しているのと理解していないのでは全く違うのもまた事実。しっかり家庭学習したいと思います。それにしても強烈な「突き」を何本も受けたO江先生、ご苦労様でした。

全国各地で大雨による災害が発生しており、被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。本県でも時折大雨が降ることもあり、今後も引き続き警戒していかなければなりません。
土曜日は中体連の試合があり、審判に行ってきました。新チームになって間もないこともあり、はじめのうちは試合にならない場面も多く見られました。しかし、リーグ戦ということもあり、試合を重ねていくうちに打ち間が分かってきたり、身体の動きが良くなったりと短時間で成長していく選手も多かったです。
この大会を主催した方の意図があったかなかったか分かりませんが、多くの試合をこなすことで実力の向上が認められたことは確かですね。
夕方からY岡町で稽古会があり、小一時間ほど稽古をさせて頂きました。若手実力者が多く参加しており、日頃あまり剣を交える機会のない方ばかりとの稽古だったので新鮮な 剣風に触れることができました。
さて、25日(月)はT八段のDVDが付録の剣道月刊誌が発売されます。本県では早期完売が予想されますのでお早めのご購入をおススメします。また、同日はT市の某有名コーヒー店で剣道具製作実演が行われるそうです。コーヒーを楽しみながら剣道具をはじめとする伝統工芸品を鑑賞するものオツなものではないでしょうか?詳しくは「あっちゃんのブログ」をご覧ください。

木曜日は仕事で高原の別荘地に行ってきました。下界が35度に対してあちらは25度。窓を開けて走ると気持ち良い風が入ってきました。オープンカーで走るともっと気持ちいいのでしょうね~。
ついでに知る人ぞ知る「大滝」に寄り、マイナスイオンをタップリ浴びてきました。驚いたのはマイナーなはずの「大滝」なのに県外ナンバーの車が何台も停まっていて、人が頻繁に出入りしていました。マイナーと勝手に決めつけていた思い込みに反省です。
夕方、仕事から帰ってくる頃の温度計は33度付近を指しており支部稽古会の厳しさを予感させます。案の定、蒸し暑く、高原の爽やかさとは対照的です。何とか最後まで倒れなかったことは幸いでした。しかし、この暑さも峠付近の気配。もうそろそろ下り坂に向かうのでしょうか。
そうそう、峠の山道には多くのトンボが飛んでおり、小さい秋を見つけましたが、本県代表の高校球児にはもう少し長い夏を堪能してもらいたいものです。

8月20日(水)の県武道館稽古会は高校生の大会のため中止です。
月曜日は約1年ぶりにH名体育館での稽古会に参加してきました。冷房完備という噂だったので、涼しいと予想していましたが、予想に反して効いているのか分からないくらい地球に優しいエコモードでした。
地元の中学生も熱心に参加しており、中には親子そろって参加されている方もいらっしゃいました。
出稽古での妙味の一つは自分の剣道が通用するか試すことが出来ることです。通用せず、打たれることも多かったですが、それも良い勉強です。
ただ、終盤暑さで思うように身体が動かなかったのが、悔やまれるところ。厳しい環境での気力体力の持続が課題ですね~。

群剣連副理事長で桐生支部長の吉田靖明先生が8月12日に逝去されました。謹んで哀悼の意を表し、お知らせ致します。
記
通 夜:8月16日(土) 午後 6時から
告別式:8月17日(日) 午前11時から
場 所:あすかホール桐生ひろさわ館(通夜、告別式共に)
桐生市広沢町3-4191-1
℡ 0277-55-0333
13日は雨が過ぎ去り、晴天で気温もそれほど高くなく、剣道をするには絶好のコンディションの中、T八段、U弟先生、O江先生の4人で毎年恒例になりつつあるW大の夏合宿にお邪魔してきました。
午前中の中盤までは基本稽古中心だったので見取稽古をしながら、最近気をつけていることを身体に染み込ませるように反復練習していました。
午前中の最後に地稽古となり、師範の先生、OBの先輩方と共に大学生と稽古させて頂きました。自分から捨てる、崩さない、崩れないことを意識しつつも、久しぶりの大学生相手に勝手が違うため、なかなかペースが掴めずに苦戦しました。しかし、大学生には大学生なりの剣道があり、それと自分の剣道とをすり合わせてどう一本に持っていくか考えるのは楽しいこと。この経験もヒントにして不十分な点を克服したいと思います。
帰りは道の駅に併設された日帰り温泉に立ち寄り、一風呂浴びて汗を流した後にビールやノンアルコールビールで乾杯。地元の野菜を使った料理に舌鼓を打ち、好日を過ごすことが出来ました。

群馬県内で行われる剣道稽古会の黙行会(もくぎょうかい)