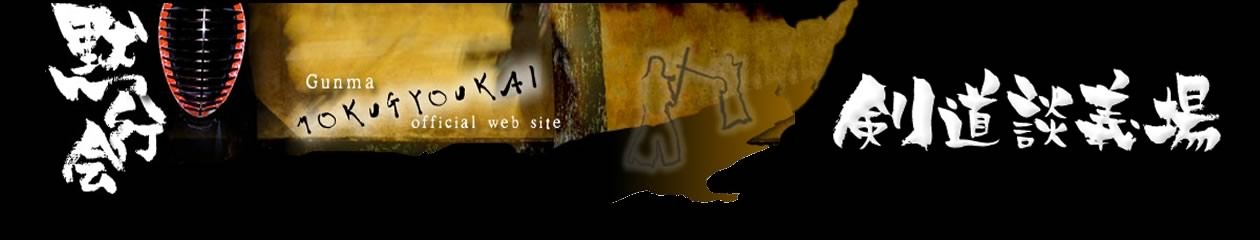先日の大統領選の決定により、政策の不確実性から日本の株価は乱高下しました。今後、日本経済の先行きにどう影響するか、興味のあるところです。
大統領選とは全く関係ないはずの木曜日の支部稽古会は過去最多人数に匹敵する大変な賑わいの稽古会となりました。大統領選の影響ではなく、全国審査会や地区の大会が間近に迫ってきた影響だとは思いますが…。
元立ちの先生方もそれなりにいらっしゃいましたが、掛り手がかなりの数に上ったため、元立ちの先生に対してそれぞれ長い列になりました。私は元立ちに立たせてもらったので中高生から大人の先生まで大勢の方と稽古ができた反面、審査前の調整にお見えになった先生にとっては見取り稽古(待つ時間)が長く、ちょっとお気の毒でした。
稽古の参加者は多い方が活気があるし、得るものは大きい気がします。アメリカの人口はまだ増えているようですが、日本は人口減少の局面に入っています。取りあえず、まだ人がいるうちに剣道しておきましょう!

日曜日は県民大会が行われ、今年はT支部の選手として出場させて頂きました。支部毎の5人の団体戦。試合前日から何となく落ち着きがなく、暴れる心を抑えるのに苦労しました。普段の稽古では全く普通なのに試合前に平常心を保つのは容易ではありません。
試合直前もあれこれ考え、高揚感も含め、心持を腹におさめるよう苦心しました。しかし、試合でしか味わえないこの緊張感、実は嫌いじゃありません。むしろ作られたテーマパークをはるかに上回る半端ないドキドキ感は何物にも代えがたいものです。
試合状況は若手の活躍もあり、チームワークも良く何とか決勝戦まで駒を進めることが出来ました。決勝では私が勝てば大将につなげたものの引き分けに終わり、結果チームは準優勝。
ある先生から「(相手の中に)入れなかったね。」と言葉を掛けて頂きました。「(図星です)そうなんです。打たれる恐さが先立ち、入り切れませんでした。」と返答しました。やはり周りで見ておられる先生方にも分かってしまうのですね~。実績ある先生に捨て切れる打ちが出せるように頑張っていきたいと思います。

世間はハロウィンで賑わっている中、仮装したい気持ちもありつつも普段と何も変わらず10月が過ぎていきました。
先日の日曜日は芝生の上で子供の剣道大会が行われました。今年で第44回目となる本大会はプログラムによれば小学生の選手だけで参加444名。ゾロ目のおめでたさも加わりました。
試合は全てトーナメントの個人戦。試合では色々なドラマが生まれました。中には悔しい思いをした選手もいるかも知れません。
早めに試合が終わったので家に帰って過去の剣道雑誌を見ていると、「魚一連、あざみの下を通りけり」という句が目に留まりました。小川のほとりにあざみの花が咲いており、その下を小魚の一群が列をなして泳いでいったという句です。
小魚たちは群れの先頭は誰だとか、本流だとか支流だとか言いながら泳いでいるのであろうが、俯瞰すればあざみの下を泳いでいった群れに過ぎないということのようです。
なるほど、剣道も人生もそう置き換えればあまり、悩まずに済むかも知れませんね。

25日の黙行会は元J大教授のK先生ご一行様をお迎えした上、多数の先生方の参加も頂き、盛況に行われました。
残念ながらK先生にお願いすることは出来ませんでしたが、K原先生やT八段との立合いを拝見させて頂きました。大学の同窓生ということもあり、打った打たれただけでなく、傍で見ている者には分からない心のやり取りを感じました。
また、大学の教え子のU兄弟先生との稽古は目を見張るものがあり、厳しくも師弟愛を感じる稽古ぶりは稽古を見守る先生方の心にも残ったのではないでしょうか?
第2道場ではK先生から剣道の伝統文化継承に対する熱い想いだったり、心根の問題だったり、格の問題だったり、ためになるお話を多数伺うことができ、たいへん有意義な時間となりました。また、一刀流のお話は奥が深く、現代剣道とは一線を画す興味深い話題でした。
さて、11月の黙行会は15日(火)と決定しました。審査前の調整も含め、先生方のご参加、よろしくお願い申し上げます。

25日(火)は黙行会となっております。
今回は前回台風で来られなかったスペシャルゲスト元J大教授のK先生他3名様が参加されるそうです。
皆様のご参加をよろしくお願い申し上げます。

田村之道先生のご尊父、田村千秋様が10月20日ご逝去されました。謹んで哀悼の意を表し、お知らせ致します。
通夜:平成28年10月22日(土)18時~
告別式:平成28年10月23日(日)12時~
喪主:田村公男(長男)
場所:通夜告別式ともに前橋市斎場
前橋市天川大島町1-31 ℡ 027-224-2777
高崎支部会員各位
西毛地区稽古会が下記の予定で開催されます。参加資格の制限は特にありませんので多数の参加をお願いします。なお、前もって藤岡支部に参加人数を伝える必要があるため、参加希望者は早めに高崎支部事務局長宛ご連絡をお願いします。
記
日時:平成28年11月13日(日) 9:30~11:30
場所:藤岡市総合学習センター 体育館
藤岡市藤岡1485番地 ℡ 0274-50-8228
連絡先:高崎支部事務局長
水曜日、T八段の大学時代の後輩で各種全国大会で活躍されている有名なY八段が来県され、K楽園でY八段を囲んで懇親を深めることができました。
個人的にはY八段が35年前に全日本学生選手権大会で優勝した時の印象が強烈に残っており、当時剣道雑誌を見ながら興奮したことを覚えています。今思えば相当なマニアックな少年だったかも知れません。
そのY先生が八段受審される先生に向けておっしゃったことは「柔らかく遣うこと」。年を取ると硬くなりがちになりますが、そこを力を抜いて柔らかく遣うことを意識すると良いとのことでした。
一流の先生から直接お話しを伺うと得るものは大きいとしみじみ実感します。こういう経験は有難いですね~。

10月に入り、日が暮れるのが早く、朝晩はめっきり冷え込んできました。この地域ではちょうど稲刈りの時期であり、市民大会の審判の先生の中には「この連休で稲刈りをしたかった。」と漏らす先生が何人かいらっしゃいました。市民大会を含め、この3連休は全国各地で剣道大会が開催された模様です。
国体は浅見先生のブログに載っている通り、開催県が優勝あるいは上位を占めたようです。本県代表チームのスコアをある先生からスマホで見せて頂き、この選手でも負けるのか!という結果を目の当たりにしてつくづく全国レベルは高いなぁと思わざるを得ませんでした。
全国と言えば、全日本学生優勝大会では寒稽古で毎年お世話になっているO体大が優勝したとのこと。つい先週お会いしたS道範士は「関西学生では優勝したけれど、そう(全日本学生)は甘くない。」という趣旨の話をされていました。師範という立場上、言葉を選ばれたのかも知れませんが、どうしてどうして、お見事な優勝です。
連休最終日の市民大会は小学生から大人まで幅広い年代で熱い戦いが繰り広げられました。私は審判を務めさせて頂き、日ごろ一緒に稽古している方々を含め、多くの試合を拝見しました。
勝った負けたはあるにせよ、各選手の頑張りを見ているとこちらも負けていられない気持ちになります。連休明けからがんばっていきましょう!

先週末はおんたけ講習会、日曜日には小学生大会の審判とハードスケジュールの剣道行事を体験することになりました。おんたけ講習会の講師はS道範士をはじめとする教士・範士の先生方が80名近くの受講生に対し熱心な講義を繰り広げられました。
金曜日の夜、S道範士に稽古をつけて頂き、頂戴した言葉は「ドタバタしている。スー!パパパッパ!とすること。」言葉の意味は痛い程よく分かります。私に足りないものの一つは素早く反応して、スムーズな足捌きをするということでしょう。技の連続性も重要なのかも知れませんね。
日曜日の小学生大会では審判をさせて頂き、有効打突に素早く反応するという面ではとても勉強になりました。いかに素早く、しかも正確に反応(判断)するか…。
今大会で剣道形の演武を披露したT兄先生の師匠である故岡範士が好んで詠われた句「おくれては 梅も桜に劣るらん 魁(さきがけ)てこそ 色も香もあれ」を思い出しました。有効打突が決まったら自分から率先して反応しなければ意味がない…くらいな気持ちで審判を務めなければダメなんでしょうね~。

群馬県内で行われる剣道稽古会の黙行会(もくぎょうかい)